野球の指導をしていて、「難しいな」と感じるのが、怒る・叱るということです。先日、相模原ボーイズの後輩コーチと食事をしている中で、「怒り方がわからない」という話が出ました。
ふと思い返すと、大学時代に僕も同じようなことを思っていて、Twitterでそれをつぶやくと、色々なことを教えてくださるフォロワーさんから一冊の本を勧められたのを思い出しました。
今回はアンガーマネジメントについて、久しぶりに本を読み返して学んだ内容をダイジェストでまとめていきます。
アンガーマネジメントとは
アンガーマネジメントとは、「怒り」という感情との付き合う方法のことです。決して”怒らない方法”ではありません。
というのも、人間には起こる必要のあるものに対しては怒り、怒る必要のないことには怒らないことが大切です。何もすべての怒りの感情を抑える必要はないのです。
「こういう時には怒る」、「こういう時には怒らない」という”線引き”を上手にしていくことが、毎日を生きやすくする近道ですし、実際の野球指導の現場でも選手との活動をスムーズにしていくことにつながります。
野球における障害予防で有名な馬見塚先生の名著、『野球医学の教科書』にも冒頭の部分でアンガーマネジメントが紹介されています。馬見塚先生の本では障害予防にとどまらず、野球界の未来のための提案が色々と紹介されており非常に勉強になります。まだ読んだことのない人は是非!指導者必携の書です。
怒りの種類を知る
怒りという感情は、生きていくのに必要な感情です。なぜなら、怒りは本来何かを守るためにある勘定だからです。動物で言えば、自分や家族が命の危険にさらされたときに怒ります。われわれ人間で言えば、立場や考え方、大切にしているものを侵されそうになったら怒りの感情が湧くようになっています。
怒りという感情を持つことは人として生きていく上で、切り離せない感情なのです。ただ、怒りの中にも良くない怒りがあるので、見ていきましょう。
・怒りのレベルが高い
→すぐに大声出す人、いませんか?
・ずっと怒っている
→「前もそうだったけど」過ぎたことを出すのはだめです
・頻度が高い
→「また怒ってる…」これも良くないですね。
・攻撃性がある
→モノや他人にあたるのは絶対NGです。
まずはこの4つに気をつけましょう。
怒りの本当の理由
僕たちの怒りの感情がどこから来るのか、これを明確にしておかなければいけません。ここで出てくるのが、「コアビリーフ」という言葉です。コアビリーフとは、あなたが日々思っている「○○べき」という信念です。
野球チームの活動で言えば、「挨拶は大きな声でするべき」「野球道具は毎日きれいに磨くべき」などです。そして、この「べき」が裏切られたとき、人間は怒りを感じるようになっているのです。
自分のコアビリーフいったいどういうものなのかを知っておくことが重要なのですが、ここで厄介な点がいくつかあります。
一つは、コアビリーフは本人にとって絶対であるということ。
二つ目に、精神状況やその場の雰囲気でコアビリーフが変わる可能性があること。
三つ目が「ある程度許せる」という範囲が存在することです。

道具を磨くように選手に言っているけれど、微妙に汚れているグローブを見て見逃してあげた、なんてことはないでしょうか?
これはおそらく、「とにかく磨くという行為が大事だ」というコアビリーフを持っているか、そのグローブの汚れが「ある程度許せる範囲だった」というパターンのどちらかでしょう。
いずれにせよ、野球指導の現場に立って、選手に厳しいことを言う場面が必ずあります。そんなわれわれには、まずは自分のコアビリーフ=べきをしっかりと見定めておく必要があるのです。
そして、自分のコアビリーフに照らし合わせて、許せない(こういうことは一緒に野球をやるうえで治して欲しい)と感じた時には、伝え方に気を付けて選手に伝える(=叱る)必要があります。
繰り返しになりますが、選手に叱ることが悪いわけではありません。その子のその先の人生において、むしろ大切なことである場合も多いです。ただ、それが感情的になってはいけないという話です。
まとめ
指導者も人間です。そして、多くの方が土日に野球指導しながら平日は学校に行ったり仕事をしたりするはずです。感情に浮き沈みがあるのは仕方のないことです。ましてや子ども相手なので、腹が立つこともあると思います。
だからこそ、自分の怒りについて、一度立止まって考えておく必要があると思っています。この辺りで今回の記事を一度まとめます。
・自分の精神状態を把握
自分は今日機嫌が悪いとわかっておくだけでも全然違います
・自分のコアビリーフを把握
自分はどんな時に怒りを感じるか、リストアップしておきましょう
・伝え方に気を付けて伝える(叱る)
上記2つに気を付けたうえで、選手に伝えなければいけないことはきちんと伝えます。
※次回は具体的な怒り方や、怒れない場合にどうするか、僕なりの考えを紹介していきたいと思います。

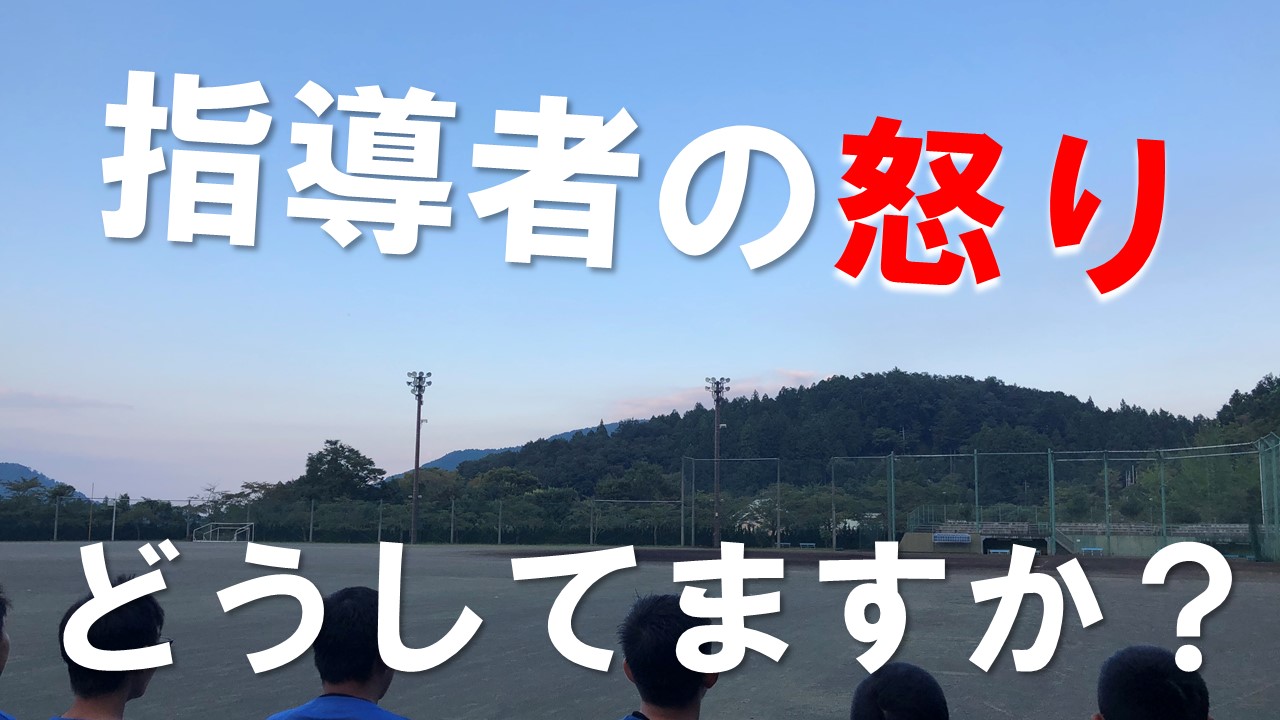




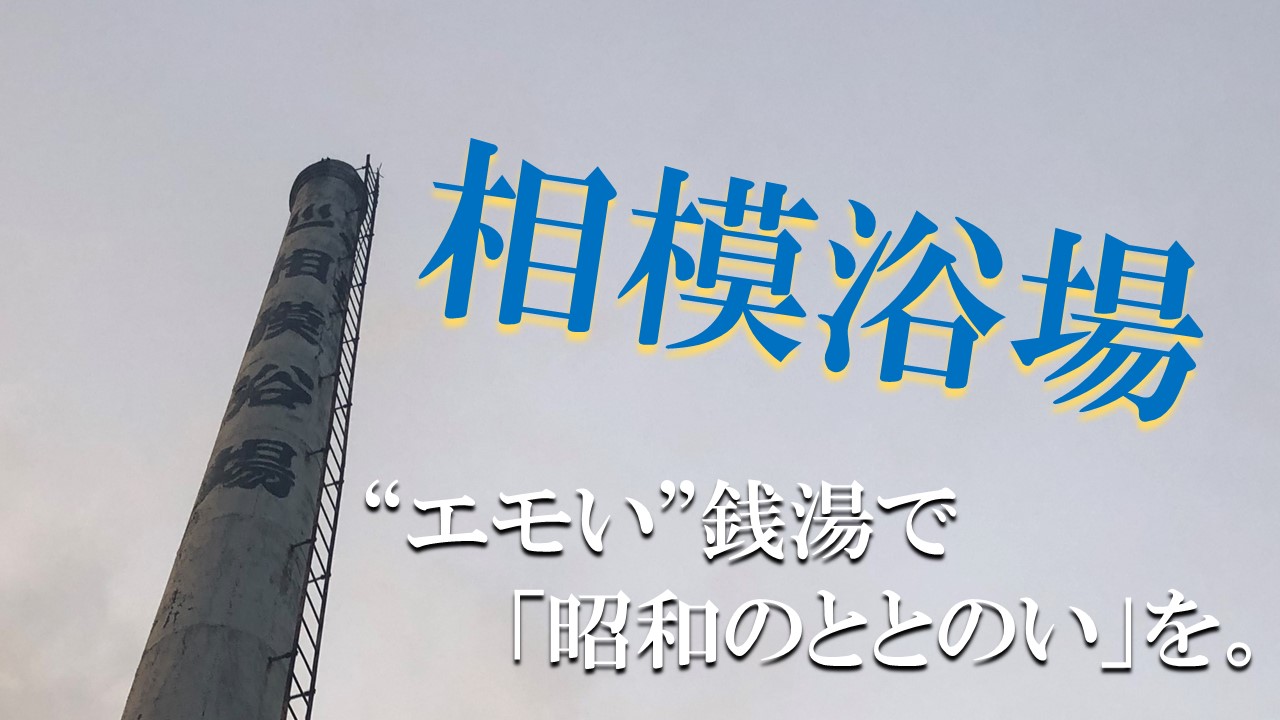
コメント